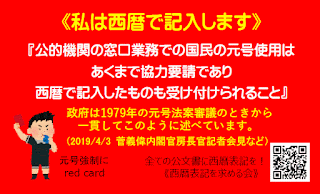100部 送料込み¥1000で頒布します。
申込みはここをクリック。
なぜ「元号レッドカード」なのか
これは、会の世話人の一人が親族の介護保険申請時に元号でなく西暦で記入したところ、「西暦だと対応が遅くなる」と言われてやむなく元号で書き直したこと、別の一人も郵便局の窓口でどうしても元号で書くように言われて憤慨していたことへの、以下の様な議論から始まりました。
1979年制定された「元号法」の審議過程から、現在に至るまで政府は一貫して「公的機関の窓口業務での国民の元号使用はあくまで協力要請であり西暦で記入したものも受け付けられる」と主張しており、これらの対応は明らかにそれに反している。
同じように、私たちが指摘した、日本年金機構の電子申請プログラムで「元号」での入力しか出来ないという事象も政府の主張に全く反しているにもかかわらず放置されている。
一方、現在の日本社会では、国内向け公文書における「元号」、民間・日常生活における「西暦」という二つの「年表記」が混在し、その換算に多大なストレスが生じているにもかかわらず、私たちが地方自治体に対して行ったアンケート結果でも明らかになったようにそのような状況に対して改善していこうという意欲がほとんど見られないという状況にある。
私たちの社会はあまりにも「元号」(世界で唯一不定期にリセットされる年の表記方式)について無頓着すぎる。こんな不合理な制度は、そのうち(いつかは)、変わらざるを得ないはずだ、などと傍観者的に見ているだけではいけない。
窓口の方々も深い考えがあって「元号」記入を求めたのではないだろう。西暦記入拒否場面や、「元号」を事前印刷した書式に出会ったら、西暦で記入した申請書に添えて窓口に出すカード、「元号」で年表記をする私たちの社会について一緒に考えましょう、というカードを作ってみたらどうだろうか。
それなら、政府は「元号は強制しない」、と言っているのだからそのルール破りに出すのは、「レッドカード」ということだね・・。
このような議論経過でした。
このカードはそうした窓口での場面だけでなく、むしろ、日常的に「元号」=私たちの社会のあり方について考えはじめるツールになってほしいと考えています。
ご存じでしたか? 政府は、省庁データの⻄暦統⼀を決定済、印刷時には元号に変換する方針!
「元号」について事実を理解していない方も多いと感ずるからです。
1.「元号」使用の根本的問題点は、不定期に、1年の途中であってさえ も、「年表記」がリセットされてしまうこと。 従って、未来の「年」は確定表記不能、「早見表」必須、という「世界で唯一の制度」。
2.「元号」の使⽤を強制する法令は存在しないが、公⽂書の元号使⽤は 「慣⾏」であると政府は一貫して主張。国外向けには一切使用せず。
3.日本社会の外国籍住民は300万人を超え、今後更に増加予想。
4.2019年に、政府は「省庁データ」を⻄暦に統⼀することを決定済み。
※印刷時には「元号」に変換する⽅針だという。
5.⽇本における「年表記」のあり方について、今こそ、私たち⾃⾝が 広く議論し、責任を持った結論を出そう!
私たちがもっとも主張したいのは5番目の「⽇本における「年表記」のあり方について、今こそ、私たち⾃⾝が 広く議論し、責任を持った結論を出そう!」という呼びかけです。
日本は年表記の方式=紀年法について議論していない国家だ
一つの結論として、これまでの元号をめぐる議論では、元号派、西暦派が全く別の論理レベルで言い合っているすれ違いの繰り返し、であることを見いだしました。
こうした日々の不便さから、もう世界標準の「西暦」にして欲しい!、という当然の要求に対して、「反論」として寄せられるのは、その社会的な不便さについてどうすべきかという具体的な議論ではなく、「元号は(中国から伝わったものだが)千三百年続いてきた日本の文化だ、「西暦」はキリスト教のものだ」「国にはそれぞれ独自の歴史や伝統があり、それが国民の精神的な一体性を確保する役割りを果たしているのであり、単純に、便利だからということで判断すべきことではない」とか、果ては、「日本人なら元号使え」というオチで打ち切られます。しかし、いくらそのように「日本人」を強調してみても、日々の西暦と元号の換算の必要性がなくなったり、元号リセットが不要になるわけではありませんから、問題は全く変化せず残されたままです。そしてその繰り返しが、結局70年以上繰り返されてきたことは、新聞の投書欄を見るとよくわかります。
要するに、最低限「統一性と普遍性」が求められる「国家における年表記の方式=紀年法がどうあるべきか」、という観点からの世論調査ではなく、諸個人の「心情」を尋ねる調査に過ぎませんでした。そして、国会においても「国家における紀年法=年表記の方式はどのような条件を具備すべきか」という観点からの噛み合った議論はなかったと言わざるを得ません。なお、「元号に関する国民の意識を調査して、今後の施策の参考とする」ために行った世論調査なのですが、政府は1977年の調査以降、元号法成立をはさみ現在に至るまで50年近く、再度の世論調査は一切行っていません。
結局、日常的な不便さ、不合理、から出発して、日本という国家において、年表記の方式=紀年法はどうあるべきかという議論、どのような国家・社会を作るべきなのか、という水準での議論を私たちは行ってこなかった。「日本の伝統・文化」という「言葉」を変更不可能な固定物であるかのように妄想し、自らをそれらに規定された存在に過ぎないと理解してしまい、「日本の伝統・文化」とは今の私たちがそれらを日々更新し、より良いものに作り上げていくべきものだ、とは考えてこなかった。具体的な問題の解決を皆で考えるのではなく、固定された抽象的な超越性によって具体的な思考の展開が阻止されてしまってきた、と見るしかないのではないか。
また、公文書=政治=公的空間においては「元号」、民間=日常生活空間においては「西暦」、という時間単位の目に見える分割が、政治・公的な領域を日常生活とは切断された別の空間として疎外してしまう認識を醸成しているに違いありません。
もし、「元号」が「日本の伝統・文化」であり、それを変更してはならないと主張するのであれば、「日本」人は世界中で唯一約30年おきに年の数え方を変更リセットしなくてはならない「呪われた民族」だということになってしまうでしょう。
《私たち》こそが、具体的な問題解決のために社会を作り上げていく主体だ
日本における選挙での投票率の低下や他国と比較した若者の意識調査の結果等を指して「社会の問題を自分事として考えよう」とか、「無力感、人ごと感は民主主義の敗北」とかいろいろと言われるわけですが、それらの言葉が越えなくてはならないのは、例えば第3次臨時行政改革推進審議会(1990-1993)が公文書の西暦併記義務化提案を土壇場でくつがえしたときの、西暦併記を「義務づけると国粋主義のような人がものを言い出して、かえって変なことになるかもしれない」という恐れ、令和改元直前の2018年「公文書西暦表記義務化見送り 政府、新元号切替で」という新聞記事での「9 月の自民党総裁選や来夏の参院選を控え、和暦を重視する保守層らの反発を避ける思惑もありそうだ。」という思惑・忖度、あるいは2018年の運転免許証有効期限の西暦化に関わるパブリックコメントへの集団的な反対意見における「日本特有の文化」という言説です。
たぶん、「愛国心」とか「日本特有の文化、伝統」というような言葉は、「平成30年~令和5年は何年間か」というような具体的な計算の不自由さとそれを改善したいという欲求を超越、無効化して、「私は私だ」という自己循環する強度だけを振り回してくるので、それを受けとめる側が、こういった言説は説得不可能、相手にしても仕方ない、と放置してしまうと、それが逆に、反論を受けないこの思考は最強だ、等と、ますます具体的な問題脈路からかけ離れて自己循環をさらに高速ではじめてしまう結果になります。
だから、すべての公文書に西暦表記を求めている私たちの会も、愛国心等の言葉でそれに反対する方たちとこそ話し合いたいと考えてきました。実際、私たちの運動に「お前ら非国民か」と絡んできてくれた方とは、どうか、あなたの「愛国心」を接地して今目の前の具体的問題について一緒に考えましょう、というメールのやり取りを試みたのですが、結局、もうメールをよこさないでくれと、相手から断ち切られてしまいました。
日本における「愛国者」と比較したら、社会というものに対する考え方は対極です。こういった試みを日本においても行うためには、まず、澱のように漂っている「日本の伝統文化」といった得体の知れないものではなく、具体的な日々の生活でそれぞれが意見を言い合って新しい「私たち」を作り上げていく、ということ、それが日本の文化そのものになるのだ、という考えへの変換が必要だと思えます。